
惻惂夵妚偺僔儈儏儗乕僔儑儞丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫶杮嫳擵
栚師
嘆惻惂夵妚偺塭嬁暘愅
嘇徚旓惻偺暋悢惻棪壔
嘊惻惂夵妚偺懝摼姩掕
嘋儔僀僼僒僀僋儖偺惻晧扴偺曄壔
嘍戝憼徣偺乽婡夿揑帋嶼乿丂
嘐惻廂偺彨棃悇寁
嘆惻惂夵妚偺塭嬁暘愅
丂憤慖嫇偱偺帺柉搣偺彑棙偵傛傝丄棃擭巐寧偐傜徚旓惻偺惻棪偑屲亾傊堷偒忋偘傜傟傞偺偼妋幚偲側偭偨丅傑偨丄暯惉嬨擭搙偐傜偼丄尰嵼峴傢傟偰偄傞強摼惻丒廧柉惻偺摿暿尭惻偑懪偪愗傜傟傞偨傔丄惻晧扴憹壛偑梊憐偝傟傞丅偟偐偟丄偙偺暯惉嬨擭搙偐傜偺憹惻偼丄宨婥懳嶔偲偟偰暯惉榋擭搙偐傜強摼惻丒廧柉惻偺愭峴尭惻偑幚巤偝傟偨偙偲偵傛傞嵿尮懳嶔偲偟偰偍偙側傢傟傞傕偺偱偁傞丅擔杮偺嫄妟偺嵿惌愒帤偺尰忬傕峫偊傞偲丄尭惻偵傛傝嵿惌愒帤傪奼戝偝偣丄晧扴傪愭憲傝偟偰傕傛偄偺偱偁傠偆偐丅徚旓惻棪偺堷偒忋偘偑彨棃偺崅楊壔幮夛偵偍偗傞夁廳側晧扴傪旔偗傞偙偲偵偮側偑傞偲偄偆偺偑戝憼徣偺尵偄偨偄偙偲偱偁傠偆丅
丂偙偺傛偆側榑棟傕棟夝偱偒側偄傢偗偱偼側偄偑丄崙柉偵徚旓惻棪傪堷偒忋偘傪擺摼偝偣傞偩偗偺嵽椏偑採嫙偝傟偰偄側偄偲姶偠偰偄傞偺偼昅幰偩偗偱偁傠偆偐丅
戝憼徣偑杮棃側偡傋偒巇帠偼丄惻惂夵妚偵偮偄偰偼丄鉱枾側寁嶼偵傕偲偯偄偨幚尰壜擻側暋悢偺夵妚埬傪採帵偡傞偙偲偱偼側偄偩傠偆偐丅崱夞偺働乕僗偱偁傟偽丄尰峴偺強摼惻丒廧柉惻偵埶懚偟偨惻懱宯傪堐帩偟偨応崌偲強摼惻丒廧柉惻傪尭惻偟丄徚旓惻傪拞怱偲偟偨惻懱宯傊堏峴偟偨応崌偵偮偄偰丄偝傑偞傑側娤揰偐傜暘愅傪偍偙側偄崙柉偑偦偺偄偢傟偐傪慖戰偡傞嵺偺敾抐嵽椏傪採嫙偡傋偒偱偼側偐偭偨偺偱偁傠偆偐丅
幚偼丄拞慮崻撪妕偵偍偄偰乽攧忋惻乿偑攑埬偲側傞傑偱偺夁掱偵偍偄偰偼丄惌晎惻惂挷嵏夛偑強摼惻丒廧柉惻偺暋悢偺尭惻埬偲戝宆娫愙惻偲偟偰暋悢偺壽惻曽幃傪採埬偟丄偦傟偵傕偲偯偔壠寁偺惻晧扴偺塭嬁摍偺帋嶼傪岞昞偟偰偄偨丅偩偑丄偙偺傛偆側帋嶼偼丄惻惂夵妚偵傛傞壠寁偺棙奞娭學傪晜偒挙傝偵偡傞偙偲偵側傞丅摉帪丄惌晎惻挷偺暘愅偵愭棫偪丄惻惂夵妚偺塭嬁暘愅傪偍偙側偭偨戝嶃戝妛偺杮娫惓柧嫵庼偺乽擭廂榋乑乑枩墌埲壓偺強摼奒憌偱偼尭惻偵側傜側偄乿偲偄偆帋嶼偼丄乽攧忋惻乿攑埬偺尨場偺傂偲偮偵側偭偨偲傕尵傢傟偨丅
丂偟偐偟丄惻惂夵妚偵偲傕側偆惻晧扴偺曄壔傪寁嶼偡傞偙偲帺懱偼丄媞娤揑側忣曬傪採帵偟丄媍榑偺嵽椏偲偡傞偲偄偆廳梫側堄枴傪帩偭偰偄傞丅
丂惻惂夵妚偵傛偭偰偁傞掱搙偺棙奞懳棫偑惗偠傞偙偲偼傗傓摼側偄偙偲偱偁傞丅尰峴惻惂偺傕偲偱晄摉偵桪嬾偝傟偰偄傞恖偑偄偨応崌偵偼丄偙傟傜偺恖乆偵晧扴傪壽偡偙偲偑岞暯側壽惻偵偮側偑傞偙偲偵側傞丅婛摼尃傪怤偝傟傞恖乆偑嫮椡偵掞峈偡傞偺偼丄摉慠偺偙偲偱偁傠偆丅夵妚偵敽偆棙奞挷惍偼丄枾幒偺拞偱偼側偔丄崙柉偵奐偐傟偨応強偱偍偙側偆傋偒偱偁傞丅
偦偙偱丄偙偺僔儕乕僘偱偼丄懞嶳惻惂夵妚偵娭偡傞僔儈儏儗乕僔儑儞暘愅傪偄偔偮偐徯夘偟丄惻惂偺偁傞傋偒巔偵偮偄偰峫偊偰偄偔偨傔偺嵽椏傪採嫙偡傞偙偲偵偟偨偄丅
嘇徚旓惻偺暋悢惻棪壔
丂暯惉嬨擭巐寧偐傜偺徚旓惻偺俆亾傊偺惻棪堷偒忋偘偵嵺偟偰丄幮柉搣偼暋悢惻棪壔傪庡挘偟偰偒偨丅偙傟偼掅強摼憌傎偳徚旓惻偺晧扴棪偑崅偔側傞偲偄偆乽徚旓惻偺媡恑惈乿傪娚榓偡傞偨傔偵丄怘椏昳偵偮偄偰僛儘惻棪側偄偟寉尭惻棪傪揔梡偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅
丂徚旓惻偺媡恑惈偼丄亀壠寁挷嵏亁憤柋挕偺僨乕僞傪棙梡偡傟偽娙扨偵妋擣偱偒傞丅昞偱偼丄暯惉幍擭偺慡悽懷偺徚旓巟弌偺僨乕僞傪棙梡偟偰擭娫廂擖偵懳偡傞徚旓惻偺晧扴棪傪寁嶼偟偰傒偨丅徚旓惻屲亾偺偲偒偺晧扴棪傪傒傞偲丄戞嘥強摼暘埵偺晧扴棪偑巐丏屲亾偱偁傞偺偵戞嘳強摼暘埵偺晧扴棪偼丄堦丏幍亾偲側偭偰偍傝丄掅強摼憌偺曽偑憡懳揑偵晧扴棪偑崅偔側偭偰偄傞丅幮柉搣偺採埬偼丄偙偺徚旓惻偺寚娮傪惀惓偟傛偆偲偡傞傕偺偱偁傞丅
丂偦偙偱丄暋悢惻棪偑嵦梡偝傟丄怘椏昳偵偮偄偰僛儘惻棪偑揔梡偝傟偨応崌偺徚旓惻偺晧扴傪寁嶼偟偰傒偨丅偨偩偟丄怘椏昳埲奜偺惻棪偼丄偡傋偰偺徚旓偵懳偟偰屲亾偱壽惻偡傞応崌傛傝傕崅偔偟側偗傟偽側傜側偄丅亀壠寁挷嵏擭曬亁憤柋挕偺暘晍傪棙梡偡傟偽丄偙偺惻棪偼榋丏屲屲亾偲側傞丅
暋悢惻棪傪嵦梡偡傟偽丄戞嘥強摼暘埵偺晧扴棪偼巐丏擇亾偵掅壓偟丄戞嘳強摼暘埵偺晧扴棪偼堦丏敧亾傑偱忋徃偡傞丅暋悢惻棪壔偼媡恑惈傪娚榓偱偒傞偙偲偵側傞丅偟偐偟丄晧扴妟偱傒傞偲戞嘥強摼暘埵偺徚旓惻晧扴偺寉尭妟偼傢偢偐擭娫敧愮墌偵偡偓側偄丅怘椏昳偵寉尭惻棪傪嵦梡偟偰偄傞儓乕儘僢僷偺崙乆偵偍偄偰晅壛壙抣惻偺昗弨惻棪偼丄廫屲亾傪挻偊傞悈弨偵愝掕偝傟偰偄傞丅尰帪揰偱偺媡恑惈娚榓岠壥偼丄彫偝偄偲偄偆尒曽傕偱偒傞丅
偟偐偟丄擔杮偺嵿惌愒帤偺尰忬傗彨棃偺崅楊壔幮夛偱偺嵿惌廀梫偺憹戝傪峫偊傞偲戝憼徣偑徚旓惻棪偺嵞堷偒忋偘傪採埬偡傞壜擻惈偼崅偄丅徚旓惻偺惻棪傪堷偒忋偘傞側傜偽丄暋悢惻棪壔偺昁梫惈偼摉慠崅傑傞偙偲偵側傞丅尰峴偺徚旓惻偺擺惻曽幃偱偼丄暋悢惻棪壔偝傟偨応崌丄壽惻昳栚偲寉尭惻棪揔梡昳栚傪挔曤忋偱暘椶偡傞昁梫偑偁傞丅暋悢惻棪壔傪嵦梡偡傞側傜偽丄儓乕儘僢僷偱嵦梡偝傟偰偄傞僀儞儃僀僗曽幃乮惻妟昜偺敪峴偵傛傝壽惻昳栚偲旕壽惻昳栚偺巇栿偑壜擻乯偺摫擖傪偼偐傞傋偒偩傠偆丅
| 昞丂徚旓惻偺媡恑惈丂丂丂丂丂丂丂丂扨埵丗枩墌丄亾 | ||||||||||
| 強摼暘埵 | 嘥 | 嘦 | 嘨 | 嘩 | 嘪 | 嘫 | 嘮 | 嘯 | 嘰 | 嘳 |
| 晧扴妟 | ||||||||||
| 徚旓惻5% | 10.9 | 13.6 | 15.2 | 16.1 | 17.8 | 19.6 | 20.9 | 22.6 | 24.7 | 30.3 |
| 暋悢惻棪 | 10.1 | 13.1 | 14.9 | 15.8 | 17.5 | 19.6 | 20.9 | 22.8 | 25.3 | 31.8 |
| 晧扴棪 | ||||||||||
| 徚旓惻5% | 4.5% | 3.7% | 3.4% | 3.1% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.2% | 1.7% |
| 暋悢惻棪 | 4.2% | 3.6% | 3.3% | 3.0% | 2.9% | 2.8% | 2.6% | 2.5% | 2.3% | 1.8% |
| 拲乯亀壠寁挷嵏擭曬乮暯惉俈擭乯亁憤柋挕傛傝嶌惉 |
嘊惻惂夵妚偺懝摼姩掕
丂惻惂夵妚偵傛傞晧扴偺曄壔傪尒傞応崌偵丄斾妑揑娙扨偵寁嶼偱偒傞偺偑強摼奒憌暿偺惻晧扴偺曄壔偱偁傞丅偙傟偼丄偄傢偽偁傞堦帪揰偵偍偗傞乽惻惂夵妚偺懝摼姩掕乿傪傒偨傕偺偱偁傞丅
丂昞偺懞嶳惻惂夵妚偵傛傞惻晧扴偺曄壔偼丄亀壠寁挷嵏擭曬乮暯惉幍擭乯亁乮憤柋挕乯偺嬑楯幰悽懷丄悽懷庡擭娫廂擖奒媺廫暘埵偺僨乕僞傪棙梡偟偰丄惻惂夵妚慜屻偺強摼惻丒廧柉惻丒徚旓惻偺晧扴妟傪媮傔偨傕偺偱偁傞丅偙偺昞偱偼丄惻惂夵妚慜偺暯惉屲擭偐傜愭峴尭惻偑奐巒偝傟偨暯惉榋擭埲崀丄徚旓惻棪偑屲亾偵堷偒忋偘傜傟傞傑偱偺奺強摼奒憌暿偺惻晧扴妟偑帋嶼偝傟偰偄傞丅丂暯惉屲擭偲暯惉榋擭偺強摼惻丒廧柉惻偺惻晧扴妟傪傒傞偲丄暯惉榋擭搙偵幚巤偝傟偨堦棩擇廫亾偺摿暿尭惻偵傛偭偰奺強摼奒憌偺強摼惻丒廧柉惻晧扴妟偼擇廫亾偩偗尭彮偡傞丅側偍丄徚旓惻偺晧扴妟偼丄暯惉屲擭偲暯惉榋擭偺惻棪偑偲傕偵嶰亾偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄偨偲偊偽戞嘦強摼暘埵偺悽懷偱偼丄敧丏幍枩墌偐傜敧丏敧枩墌傊丄愮墌偩偗憹壛偟偰偄傞丅偙傟偼丄徚旓惻偺惻棪偑摨偠偩偲偟偰傕丄強摼惻丒廧柉惻偺尭惻偑峴傢傟偨応崌丄徚旓巟弌偑憹壛偟丄偦傟偑徚旓惻偺晧扴妟偺憹戝傪惗偠傞偙偲傪帋嶼偱偼憐掕偟偰偄傞偨傔偱偁傞丅暯惉幍擭丄暯惉敧擭偵偼丄摿暿尭惻偼堦棩廫屲亾偵側傞偑丄惻棪昞偺夵惓偲壽惻嵟掅尷偺堷偒忋偘偑壛傢傞偨傔偵丄奺悽懷偺強摼惻丒廧柉惻偺晧扴妟偼堦憌掅壓偡傞丅
丂暯惉嬨擭偵偼丄堦棩廫屲亾偺摿暿尭惻偑懪偪愗傜傟丄惻棪昞偺夵惓偲壽惻嵟掅尷偺堷偒忋偘偵傛傞惂搙尭惻晹暘偺傒偲側傞偨傔丄強摼惻丒廧柉惻偺晧扴妟偼暯惉幍丄敧擭傛傝傕廳偔側傞丅
暯惉屲擭傪惻惂夵妚慜偺婎弨帪揰偲偡傞偲丄暯惉榋擭偐傜暯惉嬨擭傑偱偺奺擭偺尭惻妟偑寁嶼偱偒傞丅暯惉榋擭偺尭惻妟偲暯惉幍丆敧擭偺尭惻妟傪斾妑偡傞偲丄戞嘳強摼暘埵偺悽懷傪彍偔偲丄暯惉幍丆敧擭偺曽偑尭惻妟偼戝偒偔側偭偰偄傞丅偙傟偼丄暯惉榋擭偺摿暿尭惻偑丄崅妟強摼幰偵桳棙側宍偱峴傢傟偨偙偲偑塭嬁偟偰偄傞丅
暯惉嬨擭偵偼丄徚旓惻棪偺堷偒忋偘偑偍偙側傢傟傞偨傔偵丄媼梌廂擖幍昐屲廫幍丏巐枩墌偺悽懷傪彍偔偲奺悽懷偺尭惻妟偼儅僀僫僗丄偡側傢偪憹惻偲側傞丅傑偨丄強摼奒憌暿偵傒傞偲丄憡懳揑偵掅強摼憌偺惻晧扴偑廳偔側傞丅偩偑丄偙偺寢壥偩偗偱夵妚偺昡壙傪寛傔傞偺偼傑偩憗偄丅
| 昞丂懞嶳惻惂夵妚偵傛傞惻晧扴偺曄壔 | |||||||||||
| 強摼暘埵 | 嘥 | 嘦 | 嘨 | 嘩 | 嘪 | 嘫 | 嘮 | 嘯 | 嘰 | 嘳 | |
| 媼梌廂擖 | 285.1 | 385.3 | 425.3 | 477.0 | 533.0 | 576.2 | 622.0 | 672.8 | 757.4 | 879.4 | |
| 暯惉俆擭 | 強摼惻 | 5.4 | 11.7 | 14.3 | 17.4 | 21.5 | 24.7 | 28.3 | 35.2 | 49.4 | 70.9 |
| 廧柉惻 | 3.3 | 6.5 | 7.8 | 10.8 | 15.0 | 18.2 | 21.8 | 26.1 | 33.2 | 44.0 | |
| 徚旓惻 | 7.4 | 8.7 | 9.4 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 18.1 | |
| 暯惉俇擭 | 強摼惻 | 4.3 | 9.4 | 11.4 | 13.9 | 17.2 | 19.8 | 22.7 | 28.2 | 39.5 | 56.7 |
| 廧柉惻 | 2.7 | 5.2 | 6.2 | 8.6 | 12.0 | 14.5 | 17.5 | 20.9 | 26.6 | 35.2 | |
| 徚旓惻 | 7.4 | 8.8 | 9.5 | 10.7 | 11.3 | 12.5 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | 18.7 | |
| 暯惉俈擭 | 強摼惻 | 3.7 | 8.7 | 10.9 | 13.5 | 17.0 | 19.7 | 22.6 | 25.9 | 37.0 | 58.4 |
| 廧柉惻 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 6.1 | 7.9 | 9.9 | 13.1 | 17.0 | 24.1 | 34.8 | |
| 徚旓惻 | 7.5 | 8.9 | 9.5 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 13.0 | 14.4 | 15.6 | 18.6 | |
| 暯惉俉擭 | 強摼惻 | 3.7 | 8.7 | 10.9 | 13.5 | 17.0 | 19.7 | 22.6 | 25.9 | 37.0 | 58.4 |
| 廧柉惻 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 6.1 | 7.9 | 9.9 | 13.1 | 17.0 | 24.1 | 34.8 | |
| 徚旓惻 | 7.5 | 8.9 | 9.5 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 13.0 | 14.4 | 15.6 | 18.6 | |
| 暯惉俋擭 | 強摼惻 | 4.3 | 10.3 | 12.8 | 15.9 | 20.0 | 23.2 | 26.6 | 30.4 | 42.0 | 63.4 |
| 廧柉惻 | 2.9 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 11.8 | 15.0 | 18.4 | 22.3 | 29.4 | 40.1 | |
| 徚旓惻 | 12.3 | 14.6 | 15.7 | 17.7 | 18.6 | 20.6 | 21.3 | 23.5 | 25.7 | 30.6 | |
| 尭惻妟 | 暯惉俇擭 | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | 16.1 | 22.4 |
| 暯惉俈擭 | 3.8 | 5.7 | 6.3 | 8.4 | 11.4 | 12.9 | 14.1 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 暯惉俉擭 | 3.8 | 5.7 | 6.3 | 8.4 | 11.4 | 12.9 | 14.1 | 18.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 暯惉俋擭 | -3.5 | -3.9 | -4.3 | -3.7 | -2.9 | -3.6 | -3.4 | -1.0 | 0.7 | -1.3 | |
| 拲乯亀壠寁挷嵏擭曬乮暯惉俈擭乯亁憤柋挕傛傝嶌惉 |
嘋儔僀僼僒僀僋儖偺惻晧扴偺曄壔
丂慜夞傒偨傛偆偵丄崱夞偺惻惂夵妚偼憡懳揑偵掅強摼憌偺惻晧扴憹壛傪傕偨傜偡丅偟偐偟丄掅強摼悽懷偺懡偔偼丄庒擭悽懷偲榁恖悽懷偱偁傞丅尰嵼偺庒擭悽懷偑惗奤偵傢偨偭偰偢偭偲丄掅強摼憌偵懏偡傞壜擻惈偼彮側偄丅堦帪揑側懝摼姩掕偲惗奤傪捠偠偨儔僀僼僒僀僋儖偱傒偨懝摼姩掕偼堎側傞偺偱偁傞丅
丂偦偙偱埲壓偱偼丄傛傝挿婜揑側帇栰偵偨偭偰丄惻惂夵妚偑壠寁偺儔僀僼僒僀僋儖傪捠偠偨惻晧扴傪偳偺傛偆偵曄壔偝偣傞偺偐傪暘愅偟傛偆丅偙偺傛偆側儔僀僼僒僀僋儖偺惻晧扴傪寁應偡傞偨傔偵偼丄僐乕儂乕僩丒僨乕僞偲屇偽傟傞悽戙暿偺僨乕僞偑昁梫偲側傞丅僐乕儂乕僩丒僨乕僞偼丄憤柋挕偺亀壠寁挷嵏曬崘亁偺壠寁僨乕僞傪壛岺偟偰嶌惉偟偨丅
丂恾偵偍偄偰幚慄偱帵偝傟偰偄傞晧扴棪偑夵惓慜偺惂搙偵傕偲偯偔夁嫀偲彨棃偺惻晧扴棪傪丄揰慄偑夵惓屻偵梊憐偝傟傞彨棃偺惻晧扴棪傪帵偟偰偄傞丅惻晧扴棪偺暘曣偼媼梌廂擖丄擭嬥廂擖丄棙巕廂擖偺崌寁偱偁傝丄暘巕偼媼梌強摼惻丄棙巕強摼惻丄屄恖廧柉惻丄徚旓惻丄徚旓惻埲奜偺娫愙惻偺崌寁偱偁傞丅惻惂夵惓屻偺惻晧扴偺帋嶼偵嵺偟偰偼丄暯惉榋擭搙偵偮偄偰偼丄掕棪擇廫亾偺摿暿尭惻偑幚巤偝傟丄暯惉幍丄敧擭搙偵偮偄偰偼掕棪廫屲亾偺摿暿尭惻偲惻棪昞偺夵惓偵傛傞惂搙尭惻偑幚巤偝傟丄暯惉嬨擭搙埲崀偵偮偄偰偼丄惻棪昞夵惓偵傛傞惂搙尭惻晹暘偺傒偑宲懕偡傞傕偺偲偟偨丅
偙偙偱偲傝偁偘偨悽戙偼丄堦嬨幍乑擭惗傑傟偺悽戙偱偁傞丅偙偺悽戙偼丄傑偝偵彨棃偺崅楊壔幮夛傪扴偆悽戙偱傕偁傞丅惻惂夵妚偼丄尭惻愭峴婜娫偺惻晧扴棪傪壓棊偝偣傞偑丄暯惉嬨擭偺徚旓惻棪堷偒忋偘偵傛傝幚幙憹惻偲側傞丅偩偑丄巐乑嵨戙屻敿偺憇擭婜偵側傞偲尭惻偺壎宐傪嫕庴偱偒傞偙偲偑梊憐偝傟傞丅榋屲嵨埲崀偺晧扴棪偼夵妚慜偺晧扴棪偲傎偲傫偳曄傢傜側偄丅榁屻偺晧扴棪偑曄傢傜側偄偺偼丄憇擭婜偵偍偗傞尭惻偑挋拁巆崅傪憹壛偝偣榁屻偺棙巕廂擖傪憹戝偝偣傞偨傔偲丄擭嬥偺暔壙僗儔僀僪偑徚旓惻憹惻傪憡嶦偡傞偨傔偱偁傞丅
偟偨偑偭偰丄崱夞偺惻惂夵妚偵傛傝尰嵼偺庒幰悽戙偺彨棃偺惻晧扴偼寉尭偝傟傞丅偩偑丄偦偺晧扴棪偼丄夵妚偵傛偭偰梷惂偝傟傞偲偼偄偊丄憇擭婜偵偼栺嶰乑亾偵傕払偡傞丅堦斒揑偵偼丄廳偄偲榑偠傜傟傞尰嵼偺惻晧扴棪偑擇嶰丏堦亾乮暯惉敧擭懳崙柉強摼斾乯偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲丄堦憌偺惻晧扴寉尭偺搘椡偑昁梫偱偁傠偆丅
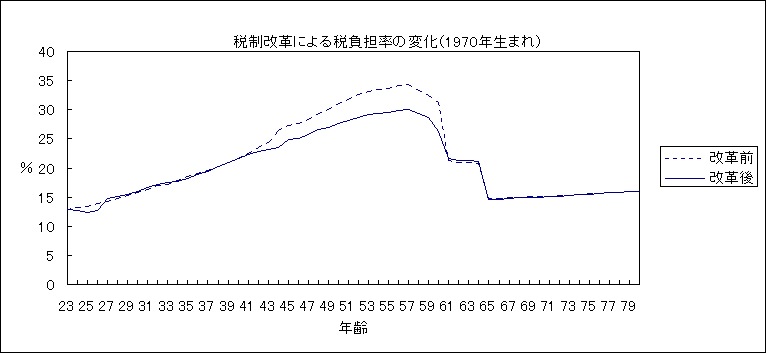
嘍戝憼徣偺乽婡夿揑帋嶼乿丂丂
丂惻惂夵妚偵傛傞壠寁傊偺塭嬁暘愅偵斾傋傞偲抧枴偩偑戝愗側嶌嬈偵彨棃偺惻廂梊應偑偁傞丅懞嶳惻惂夵妚偺夁掱偵偍偄偰丄戝憼徣偼丄暯惉榋擭屲寧擇廫幍擔偵乽惻惂夵妚偵娭偡傞婡夿揑帋嶼乿傪岞昞偟偨丅偙偺帋嶼偵傕偲偯偒丄摉弶戝憼徣偼丄徚旓惻偺惻棪傪屲亾偱偼側偔丄幍亾傑偱堷偒忋偘傛偆偲偟偰偄偨丅
偙偺帋嶼傪嵍塃偟偰偄偨偺偼丄乽柤栚惉挿棪乿乽惻廂抏惈抣乿乽帺慠憹廂乿偺俁偮偺僉乕儚乕僪偱偁傞丅挿婜揑側惻廂偺廂巟傪梊應偡傞偵偼丄彨棃偺乽柤栚惉挿棪乿偑偳偺偔傜偄偺悈弨偵側傞偐偑廳梫側堄枴傪帩偭偰偔傞丅宱嵪偑惉挿偡傟偽丄摉慠壽惻儀乕僗傕憹壛偡傞偨傔惻廂傕憹戝偡傞偙偲偵側傞丅偝傜偵丄傢偑崙偺惻懱宯偼椵恑峔憿傪帩偮強摼惻傪拞怱偲偡傞偙偲傕偁傝丄宱嵪偑惉挿偟柤栚強摼偑憹戝偡傞偲丄傛傝崅偄惻棪嬫暘偵墴偟忋偘傜傟傞偲偄偆乽僽儔働僢僩丒僋儕乕僾乿偲屇偽傟傞尰徾傕惗偠傞偙偲偵側傞丅偙傟偵傛傝堦斒偵惻廂偺怢傃棪偼丄柤栚宱嵪惉挿棪傪忋夞傞偙偲偵側傞丅乽惻廂抏惈抣乿偲偼丄柤栚惉挿棪偑忋徃偟偨偲偒偵偳偺掱搙惻廂偑憹戝偡傞偐傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅惻廂抏惈抣偑堦傪挻偊傞偲偒偼丄柤栚惉挿棪偺忋徃傪惻廂偺憹壛棪偑忋夞傞偙偲偵側傞丅乽帺慠憹廂乿偲偼丄偙偺傛偆側僾儘僙僗偵傛傝摉弶偺惻廂傛傝傕憹戝偟偨惻廂晹暘偱偁傞
丂戝憼徣偺婡夿揑帋嶼偱偼丄柤栚惉挿棪傪屲亾丄惻廂偺抏惈抣傪堦丏堦偲壖掕偟偰偄傞丅偙偺戝憼徣偺婡夿揑帋嶼偵偮偄偰偼丄偄偔偮偐偺夵慞偡傋偒揰偑巜揈偱偒傞丅
丂戞堦偺栤戣揰偼丄惻惂夵妚偵傛傞宱嵪岠壥偵偮偄偰偼慡偔峫椂偝傟偰偄側偄揰偱偁傞丅宨婥懳嶔偲偟偰強摼惻尭惻傪峴偊偽宱嵪惉挿棪傪墴偟忋偘傞岠壥傪帩偪丄媡偵彨棃偺徚旓惻棪偺堷偒忋偘偼惉挿棪傪堷偒壓偘傞岠壥傪帩偮丅偙偺傛偆側儅僋儘宱嵪偵梌偊傞岠壥傕峫椂偡傞偨傔偵偼丄柉娫偺尋媶婡娭傗宱嵪婇夋挕側偳偺宨婥梊應偺偨傔偺儅僋儘儌僨儖偺悇寁寢壥傪棙梡偡傋偒偩傠偆丅
丂戞擇偺栤戣揰偼丄惻廂偺抏惈抣堦丏堦偲偄偆悢帤偑丄夁嫀偺惻廂偲惉挿棪偺僨乕僞傪嶲峫偵偟偰丄愝掕偝傟偰偄傞揰偱偁傞丅摑寁僨乕僞傪慿傟偽丄夁嫀偺惻廂偲惉挿棪偺曄壔棪偐傜惻廂偺抏惈抣偼娙扨偵寁嶼偱偒傞丅偟偐偟丄偦偺抏惈抣偼偁偔傑偱傕夁嫀偺惂搙夵惓傪斀塮偟偨抣偲側傞丅崱夞偺惻惂夵妚偺傛偆偵丄強摼惻偺惻棪昞偺夵惓傪偲傕側偆応崌偵偼丄夁嫀偺惻廂偺抏惈抣偑彨棃偺梊應偵栶棫偨側偄丅
丂偙傟傜偺栤戣揰偺偆偪慜幰偵偮偄偰偼丄杮奿揑側儅僋儘儌僨儖傪峔抸偡傞昁梫偑偁傞偺偵懳偟偰丄屻幰偺栤戣揰偼斾妑揑娙扨偵崕暈偡傞偙偲偑偱偒傞丅偦偙偱師夞偼丄惻惂夵惓屻偺彨棃偺惻廂偺抏惈抣傪悇寁偟丄撈帺偵惻廂偺彨棃悇寁傪帋傒傛偆丅
嘐惻廂偺彨棃悇寁
丂慜夞巜揈偟偨傛偆偵丄惻惂夵妚傪敽偆応崌偵偼丄夁嫀偺抏惈抣傪梡偄偨彨棃偺惻廂梊應偺怣棅惈偼掅壓偡傞丅偦偙偱丄夵妚屻惻惂偺傕偲偱偺惻廂偺抏惈抣傪悇寁偟偰傒傛偆丅
惻廂偺抏惈抣傪媮傔傞応崌丄嵟傕拲堄偡傞昁梫偑偁傞偺偑強摼惻偺惻廂抏惈抣偱偁傞丅偲偄偆偺偼丄強摼惻偼椵恑峔憿傪帩偮偺偱惻晧扴偺憹壛棪偑強摼偺憹壛棪傪忋夞傞偙偲偵側傝丄抏惈抣偑堦傪挻偊傞偙偲偵側傞偐傜偱偁傞丅堦曽丄朄恖惻偲徚旓惻偼斾椺惻偱偁傞偺偱丄彨棃惉挿棪偑埨掕揑偵悇堏偟丄偐偮朄恖惻偲徚旓惻偺壽惻儀乕僗偑惉挿棪偲摨偠斾棪偱憹壛偡傞偲壖掕偟偨応崌偵偼丄抏惈抣偼傎傏堦偲峫偊偰傛偄丅偦偙偱丄埲壓偱偼強摼惻埲奜偺抏惈抣偼堦偲壖掕偟丄強摼惻偺抏惈抣偺傒傪悇寁偟傛偆丅
丂強摼惻偺抏惈抣偼丄尰幚偺強摼暘晍偵暯惉嬨擭偺強摼惻朄傪揔梡偟丄惻妟傪嶼弌偡傞偙偲偱悇寁壜擻偱偁傞丅埲壓偱偼丄擔杮惗妶慻崌楢崌夛偵傛傞亀壠寁挷嵏乮暯惉榋擭乯亁偺屄昞僨乕僞傪棙梡偟偨丅偙偺僨乕僞偱偼丄晇偲嵢偺廂擖丄晑梴壠懓偺擭楊側偳偑宖嵹偝傟偰偄傞偨傔丄憤柋挕偺亀壠寁挷嵏擭曬亁偺廤寁僨乕僞傛傝傕惓妋偵奺悽懷偺惻妟傪嶼弌偱偒傞丅偙偺屄昞僨乕僞偐傜偼丄強摼惻偺抏惈抣傪媮傔傞偲丄暯惉屲擭惻惂偵偮偄偰偼擇丏榋堦丄暯惉嬨擭惻惂偵偮偄偰偼擇丏巐幍偲偄偆抣偑摼傜傟偨丅惻惂昞偺夵惓偵傛傝丄抏惈抣偑掅壓偡傞偙偲偵側傞丅
丂偙偺抏惈抣傪棙梡偟偰丄崙惻憤妟偺彨棃梊應傪偍偙側偭偨丅彨棃偺柤栚惉挿棪偵偮偄偰偼俁亾偲俆亾偺俀偮偺働乕僗傪憐掕偟偨丅傑偨丄暯惉俈擭係寧偐傜偼徚旓惻偺惻棪偑3亾偐傜5%偵堷偒忋偘傜傟傞傕偺偲偟偨丅恾偱偼丄1995擭傑偱偑夁嫀偺惻廂丄偦傟埲崀偑梊應傪帵偟偰偄傞丅偙偺恾傪傒傞偲傢偐傞傛偆偵彨棃偺惻廂梊應偵偮偄偰偼丄惉挿棪偺堘偄偵傛傝戝偒偔嵎偑惗偠偰偍傝丄惻廂梊應偺擄偟偝傪帵偟偰偄傞偲傕尵偊傛偆丅

Copyright(c) 1999丂 by Kyoji Hashimoto
Last Updated 99/09/09 21:07:23