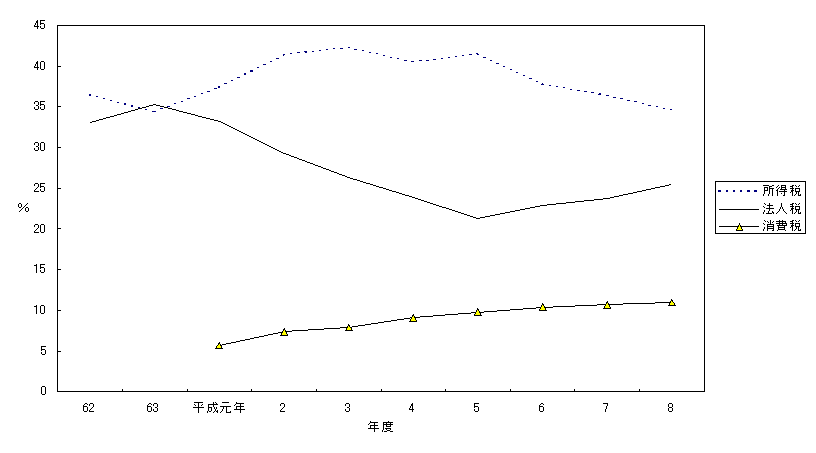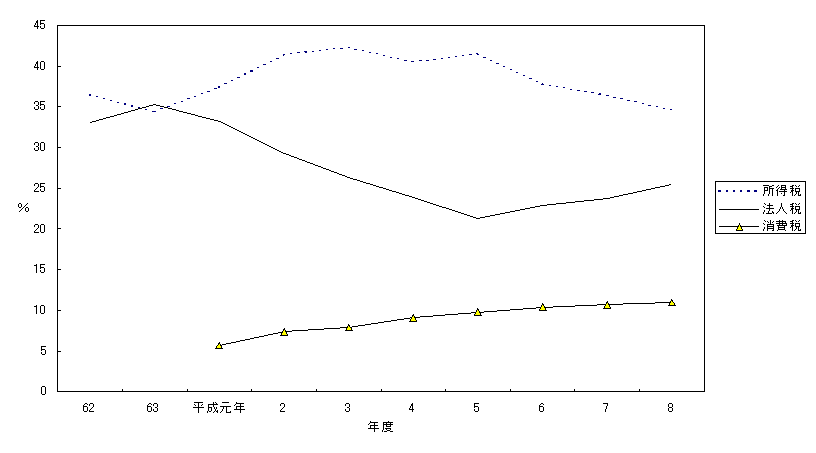引当金・準備金の見直しと法人税改革の課題
関西大学経済学部助教授 橋本恭之
1.はじめに
1997年7月12日の日本経済新聞によると、経団連は、法人税の基本税率の5%以上引き下げを要求するとともに、貸倒引当金や退職給与引当金など引当金制度の全廃も視野に入れた検討を始めたようである。現在の厳しい財政状況の中で法人税率の引き下げによる純減税のみを主張することには無理があるという判断のようだ。この課税ベースの拡大と引き換えに法人税率の引き下げをおこなうという考え方は、昨年来から大蔵省が目指していた法人税改革の方向性と合致するために、この案で経済界がまとまるならば今年度における法人税改革の実現性が高まることになろう。
しかし、個人所得税の場合と異なり、法人税における課税ベースの拡大と基本税率の引き下げは、単年度においては税収中立を確保できたとしても、長期的には純減税をもたらすことになる。というのは、たとえば貸倒引当金の廃止は、短期的には課税ベースを拡大させるが、将来時点で実際に貸倒が発生した場合には当然のことながら損金算入されるために、長期的にみて税収中立が保たれるわけではないのである。
したがって、いま大蔵省のシナリオにそって、課税ベースの拡大と引き換えに基本税率を引き下げるという改革のみを拙速におこなうことは、将来発生するであろう法人税の純減税効果に対処するための財源調達の問題を先送りにし、法人税改革の課題を各種引当金制度の見直しのみに矮小化することにつながるであろう。
法人税改革における本当の課題は、法人への所得課税という考え方そのものが限界にきているところにある。本稿では、法人税改革の課題を各種引当金の見直しのみに限定することなく、なぜ法人に課税するのか、法人に課税するならば課税ベースとして何が望ましいのかという基本的な問題に立ち返って、法人税改革の方向性について議論しよう。
2.なぜ法人に課税するのか
法人課税の根拠としては、従来から法人実在説と法人擬制説という2つの異なる考え方が主張されてきた。法人実在説とは、法人を独立の法的人格を認められた実体として捉え、経営者によって運営される独立の意思決定単位であり、法人自体が担税力をもつという考え方である。一方、法人擬制説とは、法人を株主の集合体として捉え、法人自体には担税力はないとする考え方である。現在での主流的な考え方は、後者の法人擬制説である。なぜならば、法人のとらえ方に関係なく、法人税の負担は、株主の配当の減少、株主に分配されなかった留保利潤の減少がもたらす株主のキャピタルゲインの減少、経営者の報酬の減少、従業員の給与の減少、製品価格の上昇などのいずれかの形で、最終的には個人に帰着することになるからである。ただし、法人擬制説においては、法人自体に担税力はないという見方においては正しいが、法人税の負担が株主にのみ帰着すると仮定していることに注意して欲しい。この法人税の帰着については、現在のところ必ずしも決着がついていない*1。法人税の帰着のゆくえを曖昧にしたままで、このまま法人税への依存を続けてよいのであろうか。
現在、主流とされている法人擬制説を採用する場合には、法人税は配当所得ないしキャピタル・ゲインに対する個人所得税の前払いとして解釈することになる。その場合、個人所得税と法人税の2重課税を調整する必要性が生じる。個人所得税と法人税の2重課税の調整方法としては、完全統合方式と部分統合方式がある。完全統合方式は、法人所得への課税は、留保所得への課税が株主のキャピタルゲインとの間で、配当所得への課税が株主の配当所得との間で、2重に課税されているとして、留保所得と配当所得のいずれについても個人所得税と法人所得税を完全に統合しようとするものである。部分統合方式は、配当所得のみを個人所得税と統合しようとするものである。
法人擬制説をとる限り完全統合方式が理想的なものとなる。しかし、実際に各国で採用されているのは、部分統合の方式である。部分統合方式には、受取配当税額控除方式と支払い配当控除方式が考えられる。
受取配当税額控除方式としては、イギリス・ドイツ・フランスなどで採用されているインピューテーション方式が有名である。これは、仮に法人税がない場合の個人の課税ベースを配当以外の課税所得、課税後配当所得、法人税を加算することで算出し、その課税ベースに累進税率を適用することで所得税額を計算し、法人段階で配当について前払いした税額を差し引くことで最終的な税額を決定するものである。この方式の利点は、株主の段階での所得水準の差による税率の違いを考慮した上で配当所得に関する2重課税の調整が可能になることである。わが国では、このインピューテーション方式ではなく、配当所得以外の所得とあわせた課税総所得金額が1,000万円に達するまでは配当所得の10%、1,000万円を超える部分については5%の配当税額控除が適用される。*2
支払配当控除方式とは、法人税の課税ベースから配当を控除するものである。法人段階での配当に課税せず、個人段階での配当に課税することで、少なくとも配当に関しては2重課税を排除できることになる。わが国では、平成2年4月1日以前は、配当部分の税率を留保部分の税率より低い税率で課税する配当軽課措置がとられていた。この措置は、配当への2重課税の軽減措置としてとられていたものである。しかし、平成2年4月1日以降、普通法人に対する法人税率は37.5%に一本化されている。
中小企業や宗教法人を含む公益法人等や協同組合に対する税制上の優遇措置も、法人擬制説では説明できない。平成9年現在の法人税の基本税率は37.5%である。しかし、資本金1億円以下の企業は、年800万円以下の所得については28%の軽減税率が適用される。また、宗教法人を含む公益法人等の収益事業や協同組合に対しては27%の優遇税率が適用される。法人税を個人所得税の前払いとして捉えるならば、法人の規模や形態によって税率に格差を設定する必要はない。この税率の格差は、法人実在説を採用するときのみに
正当化される。
すなわち、現行の法人税制は、法人擬制説と法人実在説の考え方をつまみ食いすることで、構築されていることになる。このような課税の根拠と現実の税制を整合的に説明することが不可能な税に、我が国は税収のかなりの部分を依存している。図1は、主要な税目について国税収入に占める比率の推移を描いたものである。昭和63年時点では、法人税の税収比率は、所得税を上回り、35.3%にも達していた。その後、平成不況による企業収益の減少に伴い、国税収入に占める法人税の比率は低下していく。平成6年以降には再び法人税の税収比率は上昇傾向にある。これは、平成6年から所得税減税が実施されたことにより、相対的に法人税が国税収入に占める比率が高まったことと、企業収益が幾分持ち直してきたことで説明できる。平成8年時点での法人税の税収比率25.5%は、かってと比べると低いと言えるものの、消費税の税収比率11%の2倍以上の水準にある。
また、この税収比率は、国際的にみるとまだまだ高い。たとえば、アメリカの法人所得税の比率は、18.7%(平成5年10月/平成6年9月会計年度決算額)、イギリスの法人税は12.3%(平成7年度実績見込額)、ドイツの法人税は2.5%(平成6年度実績見込額)、フランスの法人税は10.1%(平成7年度実績額)となっている。したがって、法人税への依存度は、先進諸国の中では際だって高いことになる。
図1 国税収入に占める比率の推移
(備考)消費税の税収には特別会計分を含まない。
(出所)『財政金融統計月報(租税特集)』各年版より作成。
しかし、現実の問題として、税収の多くを法人税に依存している以上、課税の根拠が明確でなく、最終的に誰の負担となるかが不明確であっても、即座に法人税の廃止をするわけにもいかない。しかし、本来税負担は、最終的には社会を構成する個人が負担すべきものである。また、近年では世界的にみて法人税の税率は、引き下げられる傾向にある。個人と違い、企業は、比較的容易に国境を超えていく。したがって、現行の法人税の最大の課題は、諸外国と比べてわが国の法人税の負担水準が適正なものといえるかにあると言えよう。
3.課税ベースの見直し
最終的な目標としては、法人税が税収に占める割合をできるだけ引き下げることが望ましいとしても、現在の我が国の財政状況は、法人税の純減税を可能にするような状況にない。課税ベースを見直し、法人税率の引き下げにより生じる税収の減少をカバーしようという発想は、大蔵省にとっては短期的には魅力的な提案である。
法人税の課税ベースの拡大策としては、退職給与引当金、賞与引当金、貸倒引当金などの引当金・準備金の廃止やフリンジベネフィットへの課税強化が挙げられよう。このうち、前者の引当金・準備金は、法人税において「所得」を会計的な立場から考えるかそれとも税法的な立場から考えるかという問題であり、後者は、個人所得税の前払いとして法人税を捉えるかどうかという問題である。
表1 主要国の税制上の引当金の概要
| | 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス |
|
(平成6年度
末残高) | 負債性引当金は原則として認められない。
| 負債性引当金は原則として認められない。
| 負債性引当金に関し、税法上は一般的な規定がなく、企業会計に従い個別に認められる。 | 負債性引当金は、引当金に関する一般的な規定に基づき一定の要件を充足すれば認められる。 |
| 貸倒引当金(注1) | 46,726億円 | × | × | 〇 | 〇 |
| 返品調整引当金 | N.A. | × | × | × | × |
| 賞与引当金 | 87,768億円 | × | × | 〇 | 〇 |
| 退職給与引当金(注2) | 139,335億円 | × | × | × | × |
| 特別修繕引当金 | N.A. | × | × | 〇 | 〇 |
| 製品保証等引当金 | 2,511億円 | × | × | 〇 | 〇 |
(注1)①個別の債権について、具体的な判断をすることなく、法定率又は実績率で繰入を認めるものについて記載。
②アメリカでは、総資産平均残高5億ドル以下の金融機関についてのみ認められている。
(注2)①退職一時金に関し、内部留保となるものを記載。
②ドイツでは、一定の要件を充たした場合に税法上、退職年金引当金が認められる。
出所:税制調査会「これからの税制を考える-経済社会の構造変化に臨んで-」平成9年1月、付属資料26頁引用。
引当金・準備金については、税法的な立場で考えると法人の所得の算定に際しては、退職給与や賞与は、実際に支出された段階で初めて損金算入されるべきである。一方、会計的な立場からは、将来確実に発生するであろう費用を今期の費用として計上することは、所得の算定上不可欠であるとされる。この引当金・準備制度については、諸外国でどのように取り扱われているかを示したものが表1である。
表によると、アメリカ、イギリスでは引当金を認めず、ドイツ、フランスではある程度の引当金が認められていることがわかる。果たして我が国の法人税制はどちらの方向へ改革すべきなのであろうか。すでに指摘したように、我が国の法人税は、理論的な説明が困難であり、その最大の存在理由は税収の確保にあると考えられる。そうであれば、法人所得を税法上で捉えるかそれとも会計上で捉えるかという問題に深く立ち入る必要性は薄い。引当金については、廃止の方向で考えるのが当面の税収確保という側面からやむを得ないところだろう。ただし、特に金融機関についてはその公共性を考慮して、経営の安全性を重視する立場から、貸倒引当金を存続するというのが妥当な線ではないであろうか。
引当金に比べると、それほど注目されていないが、フリンジベネフィットへの課税問題は、所得税の公平性の確保の見地からは重要な意味を持っている。我が国の多くの企業は、本来ならば従業員が個人的に支出しなけばならない費用を福利厚生費として支出してきた。代表的な例としては、従業員の住居に対する家賃補助や市場価格と比べると極めて安い社宅の提供が挙げられる。その他、大企業であれば保養地における格安の別荘などの利用も可能である。これらの現物給与は、現行税法のもとでは家賃などは一部が課税対象となるが、福利厚生費のすべてが課税されるわけではない。この現物給与への課税は、個人段階で捉えることが難しいことを考えると、法人段階で個人所得課税の前払いとして課税する方が徴税コストの面でも有利であろう。
4.所得課税・資産課税改革の必要性
すでに、指摘したように法人税の改革の方向として、課税ベースの拡大をはかり、法人税率の引き下げをおこなうことは、長期的には法人税の実質減税となる。この減税財源の問題に目をつぶり、当面の税収中立のみを達成するような法人税改革は、問題を先送りにし、将来に禍根を残すことになろう。法人税を改革するならば、所得課税・資産課税改革も含めて議論すべきではないだろうか。
先に実施された村山税制改革においては、「高齢化社会を支える勤労世代に過度に負担が偏らないよう、世代を通じた税負担の平準化」に重点をおき、所得税を減税し、消費税の税率引き上げが実施された。この基本的な考え方は理解できるとしても、所得税については主として課税最低限の引き上げと税率区分の引き上げがおこなわれただけであり、多くの課題を積み残している。
法人税を減税するならば、個人所得税の方で税収を確保するという考え方もあろう。現行の所得税制のもとでは、資産性の所得については極めて不明確な形で課税されている。株式の譲渡所得へのみなし課税は、その典型である。現行税制のもとで、株式の譲渡所得は、売却額の1%のみなし課税と申告分離課税が選択できる。みなし課税とは、株式の売却額の5%が利益であるとみなして、その利益に20%の税率で課税するものである。この場合、5%以上の利益が生じても課税対象とならないことになる。このみなし課税を廃止し、株式の譲渡益へ課税するためには、納税者番号の導入をはかり、個人の資産所得の正確な把握をはかることが欠かせない。ただし、株式の譲渡益課税を実施し、かつ総合課税化を図るのであれば、現行の所得税の一層のフラットが必要となろう。現行の所得税・住民税の最高税率は、国税の50%と地方税の15%を合計すると65%にも達する。これでは、最高税率が適用される個人にとって、株式投資は何の魅力もないことになる。望ましい税体系を考えるさいの尺度としては、公平性に加えて、効率性がある。効率性の観点からは、所得税・住民税の最高税率の大幅な引き下げや譲渡所得に対しては、分離課税と適用することも考えられよう。
5.地方法人課税改革の必要性
我が国の法人税の負担水準の議論においては、地方税としての法人課税の問題が指摘されてきた。大蔵省が試算している法人所得課税の表面税率の国際比較では、国税だけならば我が国の税率水準は、諸外国と大差ないことが示されている。しかし、地方税としての法人への課税を減税することは、地方分権の流れに逆行することになろう。また、法人税の課税の根拠は、国税よりむしろ地方税の方が説明しやすい。地方税としての法人課税は、公共サービスの対価として法人にも負担を求めるべきであるという応益原則の考え方になじむものとされている。
しかし、現行の地方税としての代表的な法人課税である事業税については、かねてから問題点が指摘されてきた。事業税は、公共サービスの対価としての性格が強調されながら、課税ベースには、法人所得が採用されてきた。このことから2つの大きな問題点が生じてきた。
第1に、事業税における地域間の税収格差の問題である。事業税における地域間の税収格差は、同一企業が複数の府県にまたがって存在する場合、本社のある首都圏で納税がおこなわれることから発生する。これまでは、事務所・事業所が2都道府県以上のまたがる分割法人については、課税ベースを従業員数で分割してきた。しかし、従業員数を分割の基準とした場合、地方の工場よりも本社の方が従業員が多く、本社のある都市圏に税収が集中してきた。そこで、1989年の改正では分割基準としての工場の従業員を5割増しとしたのだが、地域間の税収格差は是正されていないのが現状である。
第2の問題点は、赤字法人への課税ができないことである。事業税における課税ベースを所得とするかぎりは、所得の発生していない赤字法人には当然課税できない。しかし、地方における法人課税の根拠を公共サービスに対する対価として捉えるならば、たとえ赤字の法人であってもある程度の税負担を負わなければならない。
これらの問題点を解消する方策として、地方制度調査会などでは、所得金額の代わりに収入金額、資本金、付加価値額などの外形標準を事業税の課税ベースとすべきという提案が行われてきた。事業税の課税ベースを外形標準化すれば、赤字法人の問題や税収の不安定性が解消されることになる。
6.おわりに
以上でみてきたように、法人税改革は、ただ単に法人税の問題のみにとどめるべきものではない。個人所得課税の改革や地方税改革に手をつけることなく、法人税のみの減税をおこなうべきではない。ただし、最近の世界の税制改革の潮流は、法人税の減税の方向にあることも確かである。たとえば、シンガポールでは1994年度には法人税率が27%まで引き下げられ、さらに25%までの引き上げが予定されている。マレーシアでも1994年度まで32%であったものが30%まで引き下げられている。税制のみが投資を決める要因ではないにしても、これまで以上に法人税の適正な負担に注意をはらわねばならない時代になったことは確かであろう。
*1我が国における法人税の帰着の実証分析については、中井英雄(1988)『現代財政負担の数量分析』有斐閣、林正寿(1991)『法人所得課税論』同文舘を参照されたい。
*2証券投資信託収益の分配については、5%(課税総所得金額が1,000万円を超えるときは、その超える部分について2.5%)の配当税額控除が適用される。